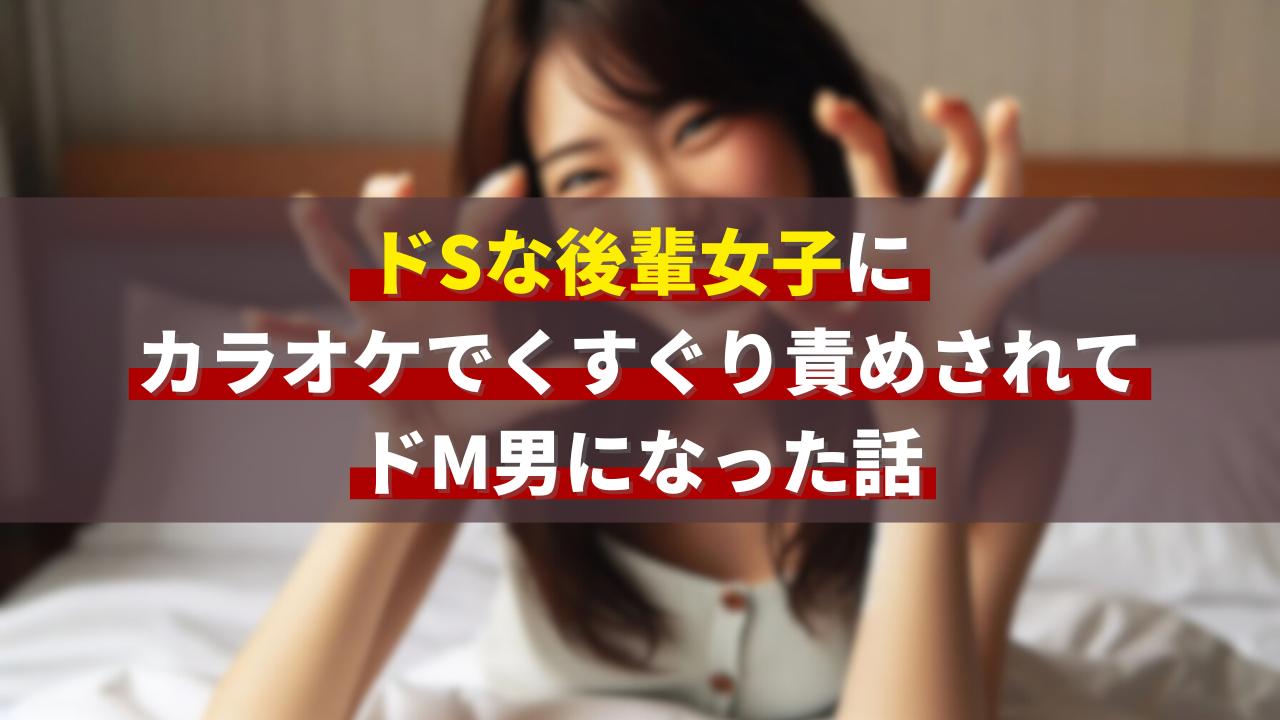こんにちは、タケルと申します。
今回は、僕が大学時代に経験したくすぐりプレイのエピソードを赤裸々に綴っていきます。
お相手は、同じゼミで知り合った1個下の後輩でした。
元々彼女はくすぐりフェチでもなければ、特徴的な性癖があったわけではないのですが…。
出会って半年もしないうちに立派なぐり(くすぐるのが好きな人)に育ってしまいました。
その勢いと技量は、普段ぐりの僕を凌駕するほど…。(めっちゃえろかった)
そんなゴッドハンドな彼女とのくすぐりプレイエピソードをご紹介します。
出会いは大学のゼミ
彼女と初めて会話をしたのは、大学3年の春でした。
控えめで、声が少し柔らかく、周りの空気をふわっと和らげるタイプの後輩です。
無防備というより、本人がまったく自覚していない“隙”がところどころに見える子でした。
ノートを取る姿勢も妙に丁寧で、ゼミ室の窓から差し込む光の中で浮かび上がる横顔には、どこか目を奪われる何かがありました。
この段階では、くすぐりフェチとしての興奮とは無縁で、ただ「距離の詰め方が自然に上手い子だな」と感じていただけです。
しかし、それだけでも十分に印象に残りました。
理由もなく距離が縮まるタイプの子はいますが、彼女はその中でも群を抜いて自然だったからです。
こちらが意識するより早く、向こうが一歩近づいてくるような不思議な感覚さえ覚えました。
そして当時の僕は、まさかこの後輩が“とんでもない才能”を秘めているなど想像すらしていませんでした。
あの控えめな雰囲気の下に、こちらの弱点をあっさり見抜き、楽しそうに攻めてくる一面が隠れていたなんて思いもしなかったのです。
徐々にセフレのような曖昧な関係に
気づけば、彼女と一緒にいる時間はどんどん増えていきました。
課題を一緒に進めるのが当たり前になり、ゼミが終われば自然と隣を歩き、気づけば終電まで話し込むほど距離が縮まっていました。
誰が見ても「仲良い先輩後輩」に見えるのに、どちらからも関係を決定づける一言が出てこないまま、不意に甘い空気だけが周囲に漂い始めていたのです。
会う頻度が増えるほど、身体の距離がゆっくりと近づいていきました。
スマホを覗き込むとき、彼女の肩がそっと触れる。
飲み物を手渡す瞬間、指先がかすかに重なる。
そのたび彼女は少しだけ視線を外しながら、どこか嬉しそうに微笑んでいました。
「……タケルさんって、意外と距離近いんですね」
そう呟く彼女の声は柔らかく、まるでからかうような仕草にも聞こえました。
けれど、その言葉を口にするのは決まって“彼女のほうが距離を詰めてきたとき”でした。
だから僕は、彼女がどこまで無自覚なのか分からないまま、ただその雰囲気に飲み込まれていったのです。
周りから見れば、ほぼカップルのような振る舞いだったと思います。
ただし形式上はあくまで先輩と後輩。
その微妙な線引きが、逆にお互いの空気をじんわり熱くしていきました。
触れた肩の温度がやけに気になり、ふとした瞬間に重なる視線が心臓の鼓動を早くします。
そんな毎日が続くことで、僕自身も彼女に惹かれていることを自覚するようになりました。
とはいえ、この時点ではまだ性癖やフェチの話なんて一切していません。
くすぐりプレイなんてもちろん頭にもなく、ただ“男女の微妙な距離感”に胸を高鳴らせていただけでした。
くすぐり好きを告白したところ、思いも寄らない結果に…
ある日、僕たちは大学近くのスタバで大学の課題をしていました。
特に深い意味があったわけではなく、ただいつもと同じように隣同士で座り、各々作業していただけです。
ところが、会話の流れの中で、僕は「自分がくすぐり好きである」という旨を口にしてしまいました。
隠すつもりだったのに、なぜかそのときだけは言葉が自然に出てしまったのです。
「……実はさ、ちょっと特殊なんだけど、くすぐりが好きなんだよね」
普通の女子なら、少し引くくらいの内容だったと思います。
僕自身も、彼女の反応をうかがいながら軽く身構えていました。
ところが、
「え、なんか意外で可愛いですねそれ。ていうか…どんな感じなんですか?」
彼女は引くどころか、目を輝かせていました。
興味津々といった表情で身を乗り出し、まるで新しい世界を見つけたかのような反応を見せたのです。
その瞬間、心臓がドクンと跳ねました。
少し照れながら、僕は軽く彼女の横腹をツンとくすぐりました。
すると、彼女は驚き半分、笑い半分の可愛い声を漏らして体を弾ませます。
その反応があまりに無防備で、思わず見惚れてしまうほどでした。
そして次の言葉が、僕の想像を完全に超えていきました。
「……ねえタケルさん。今度は私にもやらせてください」
まさかの逆リクエスト。
この一言で、空気が一気に変わりました。
僕が攻める側だと思い込んでいた関係が、静かにひっくり返されたのです。
試しに少しだけ触れた彼女の指先は、驚くほど的確でした。
最初はぎこちないはずなのに、なぜか要点を外さない。
触れる角度も、指の使い方も、圧の強さも、妙に上手いのです。
「なんか…コツ掴めそうな気がします…」
そう言って笑う彼女の表情は、普段の控えめな雰囲気とはまるで違っていました。
どこか得意げで、ほんの少しだけSっぽい。
そのギャップがあまりに強烈で、背中にぞわぞわとした感覚が走ります。
この瞬間、僕は気づきました。
「あ、これ勝てないやつだ」と。
彼女は生まれながらのドSだったのです。
カラオケに行く度に馬乗りされた話
本格的に僕らの“主導権”がひっくり返ったのは、大学近くのカラオケでの出来事でした。
二人きりの個室に入り、ドアが閉まった瞬間の静けさが、やけに意味深に感じられたのを覚えています。
「タケルさん、ちょっとだけ試してみてもいいですか?」
彼女がそんなことを言ったとき、僕は軽いじゃれ合いの延長くらいに思っていました。
ところが次の瞬間、彼女は迷いなく僕をソファに押し倒し、そのまま腰を乗せてきたのです。
想像していなかった体勢に、呼吸が一瞬止まりました。
腕を軽く押さえられただけなのに、不思議と力が抜けてしまうあの感覚。
そして、逃げ場のない姿勢のまま、彼女の指先がゆっくりと腋のあたりへ近づいてきます。
「ここ……弱いって言ってましたよね?」
その声が、妙に自信に満ちていました。
次の瞬間、僕の身体は反射的にのけぞり、言葉にならない声が漏れそうになるのを必死でこらえることになります。
彼女はその反応を見た瞬間、明らかに“スイッチ”が入ったようでした。
指先でなぞる…。
急に止める…。
また攻める…。
息が乱れた瞬間に、さらに追い込む…。
彼女は完全に僕の反応を読み切り、わざと焦らすようにペースを変えてきます。
理性が追いつかず、身体だけが熱くなるあの感覚。
「……あれ?タケルさん、ちょっと様子おかしくないです?」
そう言いながら、彼女は僕の顔を覗き込んできました。
その目つきは、僕の“動揺の理由”を完全に理解している人間のそれでした。
逃げようとしても身動きが取れず、視線をそらすことすらできません。
彼女はそんな僕の反応を楽しむように、少し意地悪な笑みを浮かべます。
「……そんなに弱いんですね、ここ」
あのとき感じた羞恥と興奮の混じったどうしようもない感覚は、今でも鮮明に思い出せます。
立場が逆転し、完全に主導権を奪われるあの瞬間。
“くすぐる側”だったはずの僕が、まさかこんな形で追い込まれるなんて、想像すらしていませんでした。
一生記憶に残り続けるであろうくすぐりセ◯クスの話
後日、後輩とラブホに行った時のことはおそらく一生記憶に残り続けると思っています。
あの日以来、彼女は僕の反応を見て、明らかに楽しんでいました。
あの“気づいてしまった女子の目”です。
僕がくすぐりに弱いだけでなく、追い込まれるほど身体が敏感になるという事実を、完璧に理解した目でした。
「……ねえ、さっきより反応大きくなってません?」
わざと無邪気な声で言いながら、指先を止める。
その一瞬の静寂が逆に苦しい。
僕が耐えようとして深呼吸したところで、再び腋を軽くなぞる。
その繰り返しが、理性を溶かしていきます。
「へぇ…ほんとに弱いんだ」
ささやくような声が耳に落ちてきて、全身が熱くなるのを抑えられません。
彼女は僕の表情をじっと観察しながら、いたずらっぽく唇をゆるめました。
「なんか…そういう顔してるタケルさん、珍しいですね」
その“珍しい”という言葉が、妙に支配的に感じられます。
逃げられない体勢、避けられない距離、僕の反応を完全に楽しむ後輩女子。
男なら誰だってそういった状況を一度は味わってみたいもの。
「そんな子、本当に存在するのかよ」とすら思ってしまいます。
でも彼女は実在したし、僕は完全に翻弄されていました。
そしてその後、彼女はさらに一言。
「……ねぇ、さっきからずっと固くなってますよ?」
彼女はくすぐるのを一度だけ止め、いたずらっぽく笑いました。
「大丈夫ですよ。私、嫌じゃないので」
その一言だけで、理性が吹き飛びそうになります。
くすぐりに弱くて、追い込まれるほど身体が反応しやすい僕の状態を、彼女はすべて理解したうえで、あえて指摘してきたのです。
そして次の瞬間、彼女は腰をずらしながら僕の胸元に顔を近づけました。
「……続き、もうちょっとだけしていいですか?」
その声があまりにも甘くて、逆らう選択肢なんてありませんでした。
彼女の指先がゆっくりと再び脇へ向かう。
もう拒めるはずがなく、ただ支配され続けるしかない状況。
フェチ心を完璧に掴まれたまま、逃げ場を失った男の無力感。
そしてその非力さを楽しむ後輩の小悪魔的な笑み。
あの瞬間の出来事を、僕は一生忘れないことでしょう。
まとめ
今回の体験を振り返って強く感じたのは、くすぐりフェチの欲望を理解し、そこに寄り添ってくれる女性は確かに存在するということです。
僕自身、最初はただの後輩だと思っていた彼女が、いつの間にか僕の弱みに気づいてしまい、主導権を握り、逃げ場を奪ってくるゴッドハンドになるなんて想像もしませんでした。
そして、そうした女性との体験は今後もずっと思い出に残り続けるでしょう。
もし「いつか自分も…」と思うなら、フェチを隠さず誠実に向き合うこと。
その一歩が、予想もしない出会いを引き寄せます。
…過去の僕がそうだったように。
あなたも一度、くすぐりの世界に足を踏み込んでみませんか?
アプリではありませんが、 2025年12月30日現在、こちらのマッチングサイトでくすぐりパートナーを見つけやすい傾向があります。
くすぐり好き(ソフトSM)が集まるコミュニティもありますので、今までアプリで出会えなかった方はチェックしてみることをおすすめします。